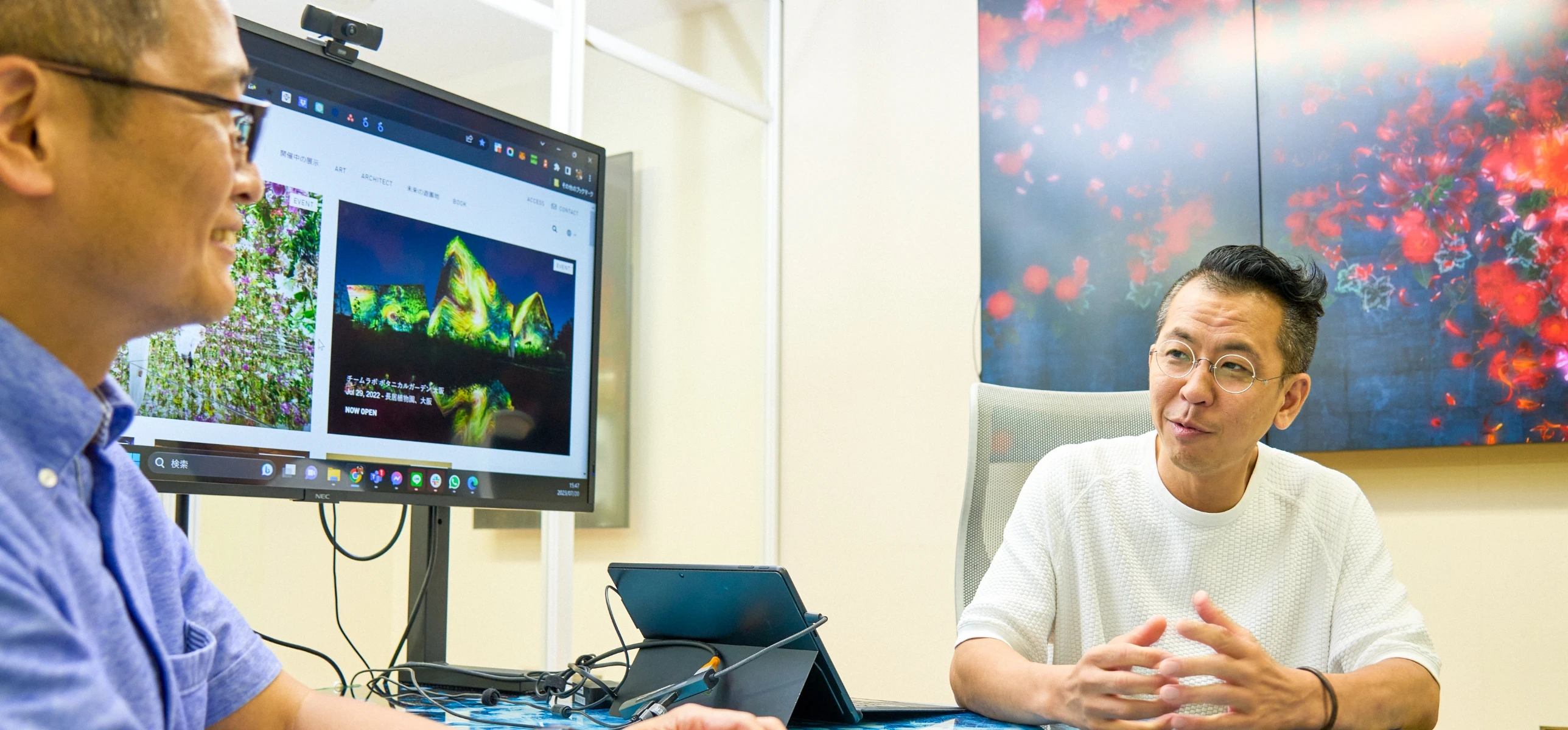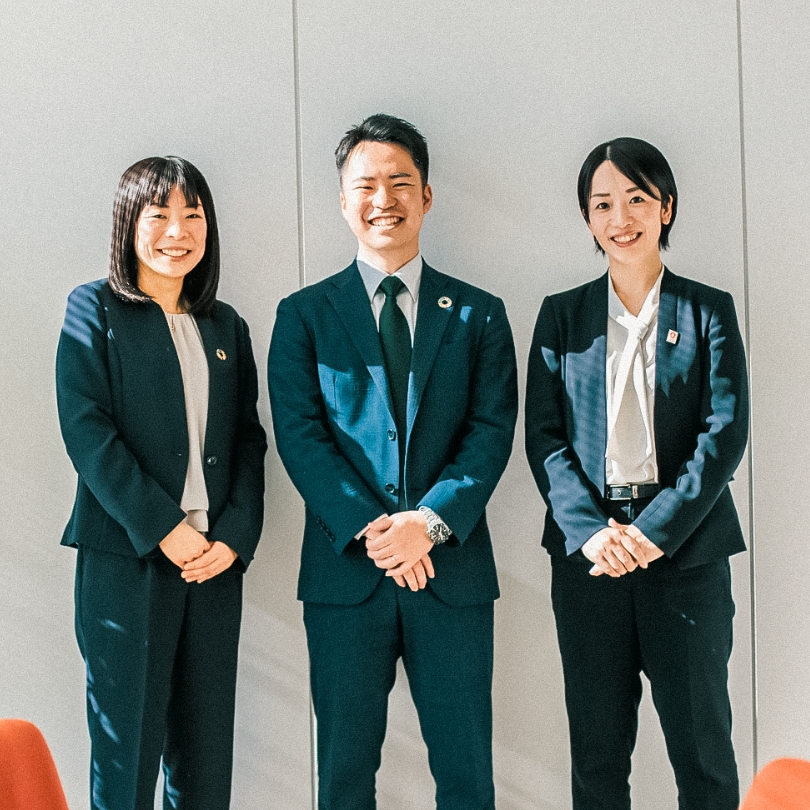talk 01
評論家ではなく、
手を動かしリアルを理解することが大切
H.K.
今日はチームラボのD.S.さんをお迎えしています。D.S.さんには、「りそなグループアプリ」を世に出すにあたって大変お世話になりました。チームラボさんは、“Resona Garage”と呼ぶオープン・イノベーション共創拠点(東京都江東区木場)におけるビジネスパートナーです。D.S.さん、出会ったばかりの頃のりそなの印象について教えてください。
D.S.
プロダクトのマネージャーとしてS.I.さん(現りそなホールディングス執行役)にお目にかかった時、「素人なんですが」と言いながら手書きのワイヤーフレームを持って来られたことに驚きました。
H.K.
チームラボさんはさまざまな大手企業とビジネスを手掛けていらっしゃいますが、それは珍しいことだったのでしょうか。
D.S.
すごく新鮮でした。しかも、いろいろ試行錯誤した形跡がある。大手企業のマネージャークラスの方が、自ら手を動かすということはあまりありません。私の勝手なイメージですが、銀行マンっぽくないなと思いました。銀行に限らず一般に大手企業の場合、プロジェクトでやろうとしていることについて、ロジックは示してくださるのですが、官僚が書いたような資料を渡され、中身はあまりないことが多いのです。りそなさんの場合、最初から手触り感があるというか、ユーザがどのように使うかということを想定して、いろいろ考えていらっしゃることが伝わってきました。ひと昔前まで、管理職になったら自ら手を動かす必要はない、という時代がありました。技術の進歩がゆっくりしていた時代はそれでもよかったのですが、今はそうではありません。インターネットが社会生活の中で当たり前のように使われる時代ですから、自ら手を動かし、リアルを理解することが重要です。
H.K.
昔ながらの銀行では、時代の変化についていけないという認識があります。一般論ですが、銀行というところは、意見は言いますが、自分で動いたり、責任を持って何かをしたりするという文化が育ちにくい環境だったと思います。評論家になってしまう人が多くなりがちな業種です。
D.S.
私も一般的な銀行というと、そういうイメージです。ところがりそなさんの場合、プロジェクトが動きだすと、「リスクは私が取ります」「そこは大丈夫。なんとかするから」といった侍のような言葉が出てくるわけです。私たちとしては、とてもやりやすいと感じました。